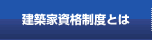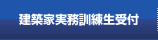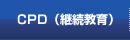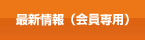|
|
|
大隈
哲
|
おおくま
さとし
|
男
|
関東甲信越支部所属
|
| 一級建築士登録番号 |
085732
|
(1974
年
2
月
20
日 登録)
|
| 住所 |
153-0064
東京都
目黒区下目黒4-19-13
|
| 電話番号 |
03
-
3714
-
6648
|
| FAX |
03
-
3714
-
6648
|
|
| 学歴 |
早稲田大學大学院理工学研究科建設工学専攻(吉阪研究室)1972年修士課程修了
|
| 職歴 |
1972年4月 日建設計入社
1977年4月~78年9月 日経マグロウヒル社「日経アーキテクテュア」編集部へ出向
|
専門領域
用途種別 |
劇場・会議場/社会教育・研修施設/図書館/屋内体育施設/大学・各種学校/病院/事務所/試験・研究施設/宿泊施設/工場・倉庫/庁舎/寄宿舎・寮
|
関連分野
業務種別 |
設計・監理
ランドスケープ
都市計画
再開発・地区整備
改修
|
| 資格・学位等 |
早稲田大学大学院理工学研究科 工学修士(1972年3月取得)
一級建築士(1974年2月20日取得)
インテリアプランナー(1988年10月1日取得)
|
| 所属団体 |
社団法人日本建築家協会(1987年~)
社団法人日本建築学会(1993年~)
社団法人インテリアプランナー協会(1988年~)
NPO都市計画家協会(2002年~)
|
| 受賞履歴 |
1971年 ペルージア都市再生国際コンペ 入賞
1981年 自治医科大学地域医療情報研修センター 照明学会照明普及賞
1986年 〃 図書館建築賞
|
| 著書・論文 |
有名建築その後(日経BP)、建築計画チェックリスト(彰国社)、図書館建築22選(東海大学)、新首都へ22の提案と提言・都心再生の視点・飯田橋交差点を考える(NUI)、建築設計資料集成交通編(丸善)、オランダの水辺環境と水管理(法政大学)
|
| 社会活動 |
「飯田橋交差点を考える会」を2000年に立ち上げ、地元方々と共に、人に優しい交差点にする社会運動や提言を行い、千代田・新宿・文京3区の行政と共に「飯田橋駅と駅周辺協議会」へと発展。「日本橋川に清流を蘇らせる会」の立ち上げに地元に協力。
|
| 代表作品1 |
|
| 作品名 | 台東区立浅草公会堂 |
| <作品にはたした役割> |
| 業務内容 | 基本設計から監理まで |
| 設計監理期間 | 1974年6月1日~1977年9月30日 |
| <作品概要> |
| プロジェクトの特徴 | 歌舞伎のできる公共ホール |
| 所在地 | 東京都台東区 |
| 用途 | 音楽演劇ホール |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階地上5階、12,185㎡ |
| 竣工年月日 | 1977年9月30日 |
| 賞・入選など | |
|
| 代表作品2 |
|
| 作品名 | 自治医科大学地域医療情報研修センター |
| <作品にはたした役割> |
| 業務内容 | 企画から工事完成後業務まで |
| 設計監理期間 | 1978年11月1日~1981年10月6日 |
| <作品概要> |
| プロジェクトの特徴 | 大学の卒後の宿泊研修室を持つ図書館と講堂 |
| 所在地 | 栃木県下野市 |
| 用途 | 図書館、講堂、研修室、宿泊室 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階地上4階、11,285㎡ |
| 竣工年月日 | 1981年10月 |
| 賞・入選など | 図書館建築賞 |
|
| 代表作品3 |
|
| 作品名 | 鶴見大学 図書館・講堂 |
| <作品にはたした役割> |
| 業務内容 | 企画から工事完成後業務まで |
| 設計監理期間 | 1983年11月1日~1986年5月30日 |
| <作品概要> |
| プロジェクトの特徴 | 貴重書庫を持つ大学の図書館と講堂 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市 |
| 用途 | 図書館、講堂、教室 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階地上3階、10,401㎡ |
| 竣工年月日 | 1986年5月 |
| 賞・入選など | |
|
| 建築に対する考え方 |
建築は、社会性と地域性のあるものである。それぞれの用途や機能に合わせ、安全で快適なことは勿論、周辺の環境や景観や街並みにも配慮する必要がある。その建物を所有する人、そこを使う人、その周囲に住む人、その街を訪れる人、それぞれに愛され長生きする建築をつくりたい。建築を取り囲む周辺環境やインフラストラクチャーも大切である。人が歩いて気持ちいい街、水辺のきれいな街をつくりだすことにも、情熱を燃やしたい。
|
| 登録建築家番号 |
20402326
|
登録建築家資格発行日 |
2006
年
11
月
1
日
|
| |
|
有効年月日 |
2028
年
3
月
31
日
|
|